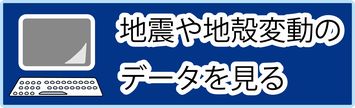| III−1 神奈川県の温泉保護対策 |
(1) 神奈川県の温泉保護対策
神奈川県は箱根や湯河原などの温泉地を抱えて、明治以後、交通手段の近代化とともに温泉開発が盛んになりました。昭和30年代にはより深く温泉井戸の掘削をして、より多くお湯を汲み上げることができるようになり、全国的に温泉の開発が進みました。ボーリング技術が発達し、汲み上げポンプの性能が良くなってきたからです。この2つの技術性能の向上が、温泉の過剰な汲み上げに拍車をかけ、温泉の枯渇が問題化していきました。
箱根、湯河原など県内の既存温泉にも影響が出て、このままでは枯渇してしまうかもしれないという危機感がありました。そこで、県は温泉の保全を目的に温泉研究所を1961年(昭和36)に設立しました。
また、温泉研究所の研究成果をもとに1967年(昭和42)「温泉保護対策要綱」を策定し、特定の地域における新たな掘削の禁止や、汲み上げ量の上限を定めました。
この要綱では、まず保護地域を定めました。「温泉特別保護地域」、「温泉保護地域」、「温泉準保護地域」の3つにランク分け、箱根、湯河原の大部分は保護地域となりました。
また、保護地域のうち温泉準保護地域の新規掘削井戸については汲み上げ量の上限を定め、箱根は1分間に70リットル、湯河原は1分間に60リットルとしております。ただし、要綱ができる前の井戸については、いままで汲んでいた分は認めています。温泉特別保護地域と温泉保護地域では新たに温泉を掘ってはいけない地域です。これを定めてから、水位の低下が緩やかになってきています。
神奈川県では温泉保護対策として1967(昭和42年)神奈川県温泉保護対策要綱を定め、温泉源の保護と適正利用を目的として温泉保護地域の指定と許認可の基準を定めています。
温泉保護対策要綱の目的及び温泉保護地域の概要については次のとおりです。
(目的)
この要綱は、温泉の枯渇、減少及び温度等の低下の防止に必要な事項を定め、もって積極的に温泉源の保護と適正な利用を恒久的に確保することを目的とする。
(温泉保護するため地域の設定)
温泉特別保護地域、温泉保護地域、温泉準保護地域及び一般地域を設定している。
保護区域の区分 新規掘削 掘削の許可 揚湯量 (1) 温泉特別保護地域
箱根町
湯本・湯本茶屋・塔の沢・須雲の一部
湯河原
宮上の一部許可しない
−
(2) 温泉保護地域
箱根町
湯本・湯本茶屋・大平台・宮ノ下・底倉・
小涌谷・二の平・元箱根の一部
湯河原
宮上の一部
山北町
中川の一部許可しない
−
(3) 温泉準保護地域
箱根町
特別保護地域、保護地域を除いた箱根町の一部
湯河原町
特別保護地域、保護地域を除いた全部
山北町
中川の一部
秦野市
鶴巻の一部
小田原市
久野の一部付近既存源泉が半径150m未満にない場合は許可
最高限度量以内
箱根町 70リットル/分
湯河原町 60リットル/分
山北町 100リットル/分
(付近既存源泉について影響調査を実施)神奈川県の温泉保護対策
図 温泉保護するため地域の設定(箱根、湯河原地域)
|
II−4 大深度温泉 |
温泉を知ろう |
III−2−(1) 温泉分析書 |